「しのぶがくし」第4号のご紹介
松川町文化財保存会の会報「しのぶがくし」第4号をご紹介いたします。
同会の令和3年度の活動報告書として発行された本書は、現地見学会や講演会の学術的な報告、会員の研究成果の発表など、地域の文化財の保存と調査を通じて地域貢献につなげる内容となっております。関係各所や松川学習センター図書室にありますのでぜひご覧ください。
会報『しのぶがくし』第4号の発行にあたって
松川町文化財保存会
会長 齋藤ミチ子
松川町文化財保存会活動の概要によると、保存会の設立は、昭和55年4月。すでに、42年の歳月が流れております。いまでも記憶に新しいのは、昭和62年発行の『松川町之文財』記念誌第一号です。それにつづいて、数々の冊子、パンフレット、文化財への標柱の設立など、松川町文化財保存の継承にご尽力されてきた諸先輩の偉大さに、改めて頭の下がる思いです。
戦国時代、伊達稙宗の三男、大森城主伊達実元の隠居城であった八丁目城。
ここを中心とした松川町の発展計画に、松川町文化財保存会も一役を担い、八丁目城曲輪の草刈りや整備に参加しました。青空に映える吾妻山脈、稲穂に染まる信夫の里の景観は、訪れた方々を魅了することでしよう。そのほかにも、歴史講演会、新春放談会。会員の皆さんと聖域を訪れ、歴史を知る楽しさを分かち合いながら、視察なども実行してまいりました。
埋もれている歴史を掘り起こせば、太古の時代からの人間模様が描かれ、それらは、変化する現代社会の手引きとなるはずです。微力ながら、様々な催しや文化財保存に関われたことに感謝を申し上げます。
コロナウィルスの感染拡大で、思い切った活動も制約されたなかで、松川町文化財保存会、会員の皆さんの知恵と努力に支えられ、会報『しのぶがくし』第4号の冊子も見事に完成しました。原稿を寄せていただいた会員の皆さん、ご支援をいただいた皆様方に、心よりお礼を申し上げます。
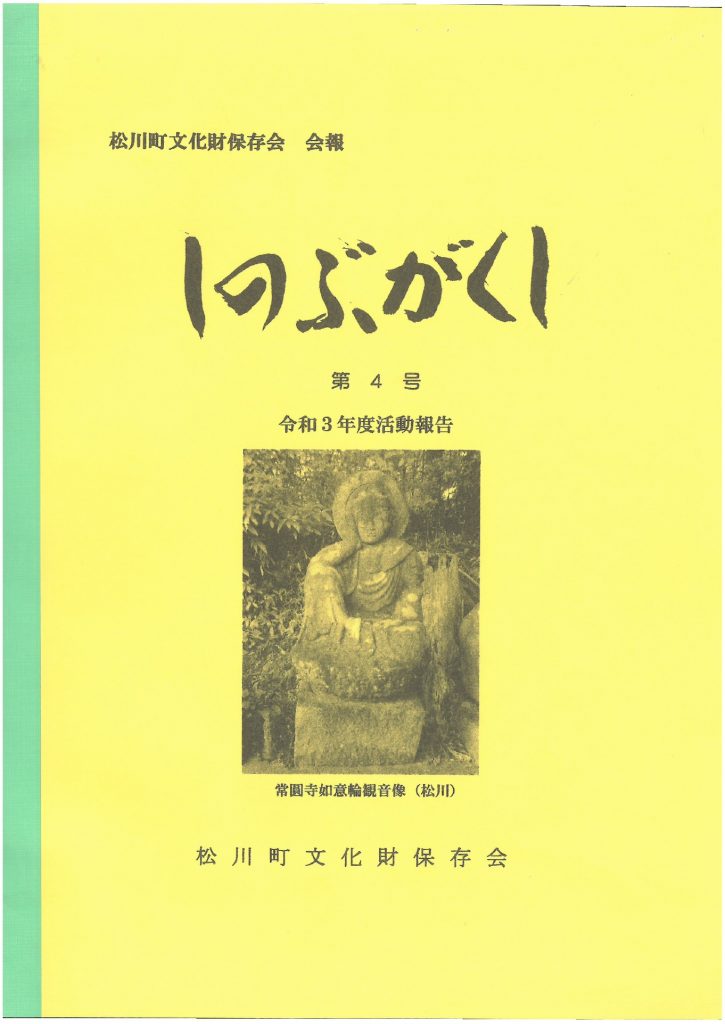
しのぶがくし第4号 目次
会報『しのぶがくし』第4号の発行にあたって
松川町文化財保存会会長 斎藤ミチ子・・・巻頭
■フィールドワーク
〇「伝説・鎌倉山の天下婆の洞窟」に参加して 和田真弓・・・1
〇ガイドマップで巡る「水原地区のフィールドワーク」
報告者 植木承子・・・7
〇松川のいしぶみ
◇松川の庚申塔を巡る 加藤一郎・・・11
◇松川の文学碑(福島市史資料叢書第48号から)を巡る 加藤一郎・・・15
〇現地見学会
「水原地区の中世城館跡」愛宕館と極楽寺舘を訪ねる 阿部正行・・・22
■展示会と講演
〇展示「幕末に八丁目宿が生んだ画家 加藤候一の世界」
報告者 加藤一郎・・・25
〇講演 展示「幕末に八丁目宿が生んだ画家 加藤候一の世界」にちなんで
「八丁目宿」 柴田俊彰先生
「加藤候一と八丁目文化」 星隆先生
報告者 植木承子・・・30
〇講演時配付資料・・・34
■歴史講演会(市民学習プラン支援事業)
伊達氏と大森城・八丁目城 福島大学名誉教授 伊藤喜良先生
報告者 植木承子・・・52
■新春放談会
〇奥州八丁目天満宮についてバートⅡ
25年に一度の御神紀祭を継承する人々の想い 佐藤清子・・・58
〇幻の実測地形図「2万分の1迅速図」で読む松川 阿部正行・・・65
〇妄想 伊達氏にまつわるこぼれ話 植木承子・・・67
〇文覚について 小野友平・・・73
■松川学習センター事業
「歴史文化財巡りウォーク下見体験記・案内記」
〇松川の文学碑と八丁目宿場町の寺社巡りコース 植木承子・・・74
〇奥州街道沿いをめぐる今昔物語コース 和田真弓・・・78
〇松川の金山と八丁目巡りのコース 斎藤ミチ子・・・84
■投稿
〇「八丁目城跡」略測図の作成 阿部正行・・・90
〇私と松川 渡部八重子・・・92
〇史跡文化財巡りウォークの感想 佐藤清子・・・95
〇松川の庚申塔(福島市文化財調査報告書第23・24号から) 加藤一郎・・・97
◎編集後記
表紙・題字/小野友平


